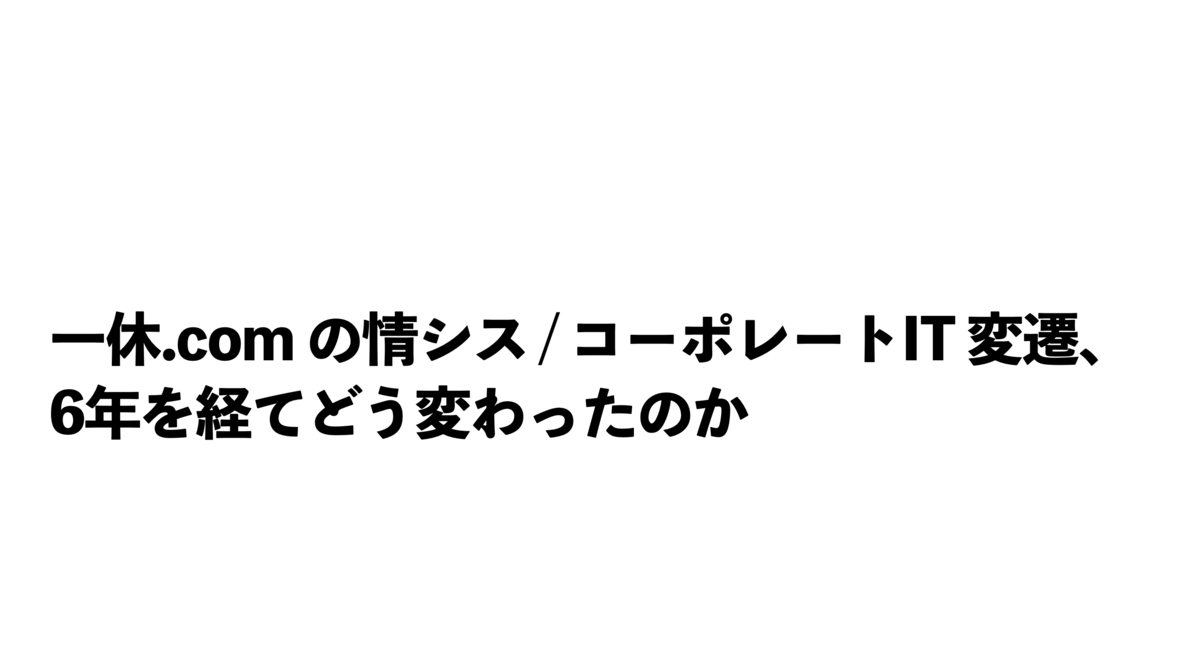
はじめに
![]() id:rotom です。社内情報システム部 兼 CISO室 所属で ITとセキュリティを何でもやります。
id:rotom です。社内情報システム部 兼 CISO室 所属で ITとセキュリティを何でもやります。
このエントリは 一休.com Advent Calendar 2024 16日目の記事です。昨日は ![]() id:naoya による TypeScript の Discriminated Union と Haskell の代数的データ型 でした。その他の素敵なエントリも以下のリンクからご覧ください。
id:naoya による TypeScript の Discriminated Union と Haskell の代数的データ型 でした。その他の素敵なエントリも以下のリンクからご覧ください。
2018年のアドベントカレンダーにて「一休における情シスの取り組み」を紹介させていただき、一定の反響をいただくことができました。 早いものであれからすでに6年が経過しました。6年も経つとコーポレートIT も変遷しています。
これまで特定の製品・サービスの事例などは断片的に紹介していましたが、6年ぶりに改めて全体像をお話したいと思います。
なお、主に私が進めてきたコーポレートIT、セキュリティ分野に注力して紹介します。ネットワーク、インフラ分野でも非常に多くの変遷・改善がありますが、同僚の ryoma-debari のエントリや、HPE 社のプレスリリースなどもご覧ください。
取り組んできたこと
組織体制の変化
before: システム本部
after: コーポレート本部

一休の情報システム部門は前身となるインフラチームからの流れを汲んでエンジニア部門に所属していましたが、部署ごとバックオフィス部門に異動しました。
情シスがエンジニアとバックオフィスどちらに所属すべきか、という議論に定説はなく各の組織文化に依る部分がありますが、一休においてはバックオフィス部門に所属することで、人事総務、財務経理、法務などとの連携が円滑になり、後述する本社オフィス移転などの大規模プロジェクトもスムーズに進めることができたと思います。
一休はここ数年で新規事業が複数立ち上がり、ビジネスとしても大きく成長しており、ともなって従業員も増加していますが、情シスのチームは非常にコンパクトに運営できており、2024/12 時点で専任の社員は2名です。 ゼロタッチデプロイやプロビジョニング、ChatOps を始め、業務の自動化・改善が進み、ルーチンワークが占める割合が減ったためです。引き続き情シスの省力化に取り組みます。
オフィスファシリティの刷新
before: 赤坂
after: 紀尾井町

長らく赤坂見附のトラディッショナルなビルに3フロア借りていましたが、2022年に当時のZホールディングス、現・LINEヤフーの本社が入居する東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワーへ移転しました。 先日は情シスカンファレンス BTCONJP 2024 の会場にもなりました。
移転のタイミングで多くのオンプレミス資産を廃棄し、昨今のインターネット企業らしいモダンなコーポレートIT へ刷新をしました。 固定電話や FAX を廃止した 話や、入退室管理などのファシリティ周りの話については、下記エントリに詳細を書きましたので合わせてご覧ください。
なお、本社移転ほどの規模ではありませんが、6年間で 支社・営業所の立ち上げは6拠点、移転は8拠点 で実施しており、ほぼ常にどこかの拠点へ飛び回っていました。地方拠点においてもオンプレミスで持つ資産は廃止を進め、本社同様に固定電話や FAX、有線 LAN を廃止した非常にコンパクトなインフラ構成になりました。
Slack Enterprise Grid 移行
before: Slack Business Plus
after: Slack Enterprise Grid

一休は2014年より Slack を利用しています、もう11年目になります。そんな10年の節目(?)にプランを最上位である Enterprise Grid へアップグレードしました。
2つあったワークスペースは1つの OrG の配下に統制され、監査ログ API やデータ損失防止(DLP:Data Loss Prevention)などのエンタープライズ組織向けのセキュリティ機能が利用可能になり、よりセキュアに利用できるようになりました。
Slack はカジュアルにコミュニケーションがとれる便利なツールである反面、情報漏えいの発生源になるリスクもあります。適切に監査・統制することで、利便性と安全性を両立していきます。

Enterprise Grid 向け機能のひとつである「情報バリア」については、2023年のアドベントカレンダーで解説しています。
デバイス管理の刷新
before: オンプレミス IT資産管理ツール
after: Microsoft Intune / Jamf Pro

以前は Windows と Mac それぞれの OS 向けの資産管理ツールをオンプレミスのサーバー上に載せており、オフィスのサーバールームで元気に稼働していました。 Windows Server の EOL のタイミングなどもあり、フルクラウド型のモバイルデバイス管理(MDM:Mobile Device Management)への移行を検討し、Windows は Microsoft Intune、Mac は Jamf Pro を選定しました。
MDM 導入前は入社準備でデスクに PC、iPhone、iPad を数十台並べてひたすらセットアップする光景が風物詩でしたが、Windows は Windows Autopilot、Mac、iPhone、iPad は Apple Business Manager と連携した Automated Device Enrollment によりゼロタッチデプロイが可能になり、キッティングにかかる工数を大幅に削減できました。
iPhone / iPad については当時すでに別の MDM が導入されていたのですが、後にリプレイスを行い、現在は Mac と合わせて全て Jamf Pro で統合管理されています。これらの製品は MDM として広く知られているものなので、詳細な説明は割愛します。
当時の一休はエンジニアも含めて Windows の割合が非常に高く、 Windows / Mac 比率 8:2 という状態からの Jamf Pro 導入でした。 マイノリティである Mac は冷遇されがちでほぼ野良管理、自己責任での利用という状態から、Jamf Pro により適切に管理・統制された状態まで進めることができました。
Windows 混在環境における Jamf Pro 導入については、 Jamf Connect も含め導入事例、プレスリリースで広く紹介していただいています。
EDR / SIEM 導入
before: オンプレミス アンチウイルスソフト
after: Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Sentinel
エンドポイントセキュリティもIT資産管理ツール同様、オンプレミスで稼働するアンチウイルスソフトを利用していました。
サーバーの保守運用コストがかかるだけではなく、デバイスへの負荷が大きい、最新 OS への対応が遅い、パターンマッチングでの検知・検疫はできる一方で、侵入後のリアルタイム検知ができないなどの課題もあり、EDR(Endpoint Detection and Response)型のセキュリティ製品へのリプレイスを検討している中で、Microsoft Defneder for Endpoint(以下、 MDE)を導入しました。
Mac については Jamf Protect という製品もありますが、Windows / Mac / iOS / iPadOS などマルチ OS に対応している点からも、Apple デバイスも MDE で運用しています。
同時期に SIEM(Security Information and Event Management)として Microsoft Sentinel を導入しており、MDE や Microsoft Defender for Identity などで検知したログは Microsoft Sentinel に集約され、インシデントは Slack に通知され、リアルタイムに検知・分析・対応ができる運用をしています。
ライセンス・アカウント管理の改善
before: Google スプレッドシート
after: Snipe-IT, Torii

Google スプレッドシートなどでがんばっていたIT資産・ライセンス管理については Snipe-IT というOSS の IT資産管理ツール(ITAM:IT Asset Management)を導入しました。 OSS なので自前でホスティングすれば費用はかからず、hosting packages を利用すればランニングコストを支払い SaaS のように利用することもできます。
Snipe-IT に登録された情報をもとに Slack に更新期日の近いライセンスを通知することで、うっかり失効してしまう、自動更新してしまい事後稟議になってしまう、といった事故を防いでいます。
また、近年では SaaS 管理プラットフォーム(SMP:SaaS Management Platform)というジャンルの、いわゆる SaaS を管理する SaaS が登場しています。国産ではジョーシスなどが有名ですが、グローバル SaaS を非常に多く取り扱う一休では Gartner の Magic Quadrant でも高く評価されている Toriiを選定 しました。
こちらでコスト可視化や Microsoft Entra ID の SCIM(System for Cross-domain Identity Management)によるプロビジョニングに対応していない SaaS の棚卸しを実施していきます。まだ導入して日が浅いため、運用設計のノウハウが溜まってきたらどこかでアウトプットできればと思います。
ヘルプデスクの改善
before: Google フォーム
after: Jira Service Management
6年前のエントリでは Google フォームでヘルプデスク対応を行っていると書きましたが、その後、Halp という製品を導入し、Halp が Atlassian に買収されたことで、Jira Service Management(以下、JSM)に統合されました。 Slack のプレミアムワークフローが無償化したことから移行も検討していますが、現時点ではまだ機能に不足を感じており、JSM での運用を続ける予定です。
従業員は Slack に普通に投稿するだけでチケットが自動起票され、クイックに対応可能です。出張や外出が多い営業社員もスマートフォンからスムーズに問い合わせができます。ヘルプデスクでよくある DM 問い合わせ問題も解決しています。
ヘルプデスク改善のあらましについては、下記エントリをご覧ください。
Slack 打刻 / 勤怠打刻自動化
before: Web アプリ / モバイルアプリ
after: Slack / Akerun 連携

一休では勤怠管理システムとしてチムスピ勤怠(TeamSpirit)を利用しています。勤怠打刻をする際は Web アプリから打刻するか、Salesforce のモバイルアプリを利用する必要がありました。 ブラウザを立ち上げて、アクセスパネルアプリケーションから TeamSpirit を開いて打刻をする、というのは少々手間であり、勤怠打刻漏れもよくおきていました。
TeamSpirit が Slack 連携機能を提供開始した際には早速設定を行い、Slack で打刻が完結するようになりました。
その後、全社で利用していた入退室カードリーダーをオンプレミスのシステムから Akerun というクラウド型のカードリーダーへリプレイスを行いました。サムターンに設置するタイプの Akerun Pro のイメージが強いかもしれませんが、オフィスビルの電子錠の信号線と連携できる Akerun コントローラーという製品を選定しました。
これによりクラウドサービス上で統合管理ができるようになっただけではなく、API を提供していることから勤怠管理システムとの連動もできるようになりました。こちらも TeamSpirit との API 連携を行うことで、オフィスに出社している際は、オフィスへの初回入室時刻が出勤打刻、最終退室時刻が退勤打刻に自動連携 されるようになりました。
パスワードマネージャー全社展開
before: 1Password (高権限者のみ)
after: Keeper

パスワードマネージャーは以前から 1Password を利用していましたが、一部の特権を持つエンジニアのみで利用されていました。 一般の従業員は個別にパスワードを管理している状態であり一定のセキュリティリスクを感じており、パスワードマネージャー全社展開を検討していました。
数百人規模に展開する際は ITリテラシーの高くないメンバーにも使っていただくことになりマスターパスワードを紛失してしまった際の懸念や、組織変更への対応の運用負荷に懸念がありました。
そこで SAML による SSO、SCIM によるプロビジョニングに対応した Keeper へリプレイスを行い、全社展開を行いました。導入時の話は事例化もしていただいたので、詳細はこちらもご覧ください。
PPAP 廃止
before: PPAP, ファイル共有ツール
after: mxHERO
一休はソフトバンクグループの会社でもあり、ソフトバンクグループは Emotet などのマルウェア対策のため、2022年にパスワード付き圧縮ファイル(いわゆる、PPAP:Password付きZIPファイルを送ります、Passwordを送ります、Angoka、Protocol)を廃止しました。
一休も従来のセキュリティポリシーでは社外へ機密性の高いファイルを送付する際は PPAP で送信するルールでした。またメディア事業など外部と大容量のファイルをやりとりするチームへは個別にファイル共有ツールのアカウントを払い出す運用を行っていました。 このセキュリティポリシーの改定と、代替となる手段の整備を進めました。
PPAP 代替ツールについても多くの製品がありますが、一休では経済産業省 などの官公庁やエンタープライズ企業でも実績のある mxHERO を導入しました。
メールの添付ファイルを自動的にファイルストレージの安全な共有リンクに変換して送信することから、誤送信をしてしまった場合もファイルを消したり、アクセス権限を解除したりすることで、情報漏えいを防止することができます。これにより PPAP を代替できると考えました。 一休ではファイルストレージとして Google ドライブを利用しているため、mxHERO と Google ドライブを組み合わせて導入することを検討しました。

しかし、Google ドライブは Google アカウントが前提となっていることが多く、Box と比較すると制限事項が多くありました。特に共有リンクに有効期限が付与できないと、共有が不要になったファイルも、設定変更を忘れると URL を知っていれば永久的にアクセスできてしまう可能性があり、解決する必要のある課題でした。 Box の導入も検討しましたが、既存のファイル共有ツールを比較するとランニングコストが大幅に上がってしまうことから断念しました。

そこで、GAS(Google App Script)によるスクリプトで対象の共有ドライブ内のフォルダを、送信日時タイムスタンプから1週間経過したら自動削除する 、という実装を行い、実質的に共有リンクに1週間の有効期限を設定することにしました。
これにより PPAP を廃止してセキュリティ上のリスクを低下できるだけではなく、従業員はただメールにファイルを添付するだけでよくなったためユーザビリティも向上し、また、ファイル共有サービスの解約によりアカウント管理などに伴う情シスの管理工数も削減することができました。
注意点としては 25MB を超える大容量ファイルは mxHERO のルーティングより Gmail 側の Google ドライブ URL への自動変換が実施されてしまうため、mxHERO 経由で送信することができません。そのため、大容量ファイルについては手動で共有リンクを発行する運用をしています。 こちらも GAS により有効期限を設定していますが、手動で発生している作業も将来的にはより自動化を進めたいと考えています。
ファイルサーバー移行・廃止
before: オンプレミス Windows Server
after: Google ドライブ ( Google Workspace Enterprise Plus )
一休には複数のオンプレミスのファイルサーバーが存在しておりましたが、AWS EC2 上への移行を経て、2023年にGoogle ドライブへの移行が完了し、完全に廃止 しました。
さらっと書きましたが、長年運用していたファイルサーバーにはブラックボックス化したマクロの組まれた Excel が潜んでいたり、情シスでもアクセスしてはいけない機微な情報を保管したフォルダがあったりと一筋縄で行くものではなく、全社を巻き込んでの数年がかりのプロジェクトでした。 ファイルサーバーの運用を行っている情シスの皆さんなら、この大変さを察していただけるのではないでしょうか・・・
なお、ファイルサーバーは複合機からスキャンしたファイルの置き場にもなっていましたが、オンプレミスのプリンタサーバー廃止と合わせてクラウドプリントに移行しており、スキャンしたファイルの置き場も Google ドライブに移行しました。
SASE 導入の見送り
before: VPN
after: 未定
一休のネットワーク構成は現時点ではいわゆる境界型セキュリティであり、社外から社内リソースへ接続する際にはリモート VPN で接続を行います。 「脱・VPN」に向けて以前より SASE(Secure Access Service Edge)の導入を検討しており、今年はいくつかの製品を PoC(Proof of Concept / 概念実証)まで実施しました。
大きな工数をかけて検証を行ってきましたが、特定の通信に対するパフォーマンス低下、開発環境への影響が PoC 期間中に解消せず見込みも立たなかったことから、残念ながら導入に至ることはできませんでした。
導入は見送りにはなりましたが、PoC を通じて貴重なノウハウを得ることができました。 脱・VPN やゼロトラストネットワークの実現に、SASE 導入は必須ではなく、あくまで1つの手段であると考えています。デバイストラストなど別のアプローチからも、ユーザビリティを両立したセキュリティを目指していく予定です。
まとめ
オンプレからクラウド / SaaS 中心のモダンな IT へ

細かなプロジェクトを上げるとキリがありませんが、ここ数年の取り組みをまとめると、オンプレミスからクラウドへの転換期であったと思います。 それ故に創業当初からオンプレミスの資産がなく、フルクラウドでコーポレートIT を構築している IT企業から見ると目新しさはなく感じると思います。
一休も外から見るとモダンなIT企業に見えるかもしれませんが、1998年に創業し間もなく四半世紀を迎える会社です。多くの資産を抱えた組織であり、クラウドへの移行やゼロトラストネットワークの実現は一朝一夕で実現できるものでありません。 クラウドサービス / SaaS も導入することは目的ではなく、その後の運用設計が重要となってきます。引き続きモダンなコーポレートIT環境を目指して最適化に向けて取り組んでいきます。
色々やった。これからどうするか
これまでは導入事例の取材や、ブログ、勉強会やカンファレンスで発表で外部へアウトプットできる、わかりやすい実績がありました。一方で、クラウド / SaaS も導入・移行フェーズが終わり運用に乗った今、今後はそういった機会も少なくなり、直近は地道な改善活動が多くなってくると思います。(これをチーム内では筋トレタスクと呼んでいます)
目下の課題が解消に向かいつつある中、いかに課題を見つけ出し、ボトムアップでチーム、組織、ビジネスの課題をテクロノジーで解決していくか、を考え筋トレのように日々改善を進めていきます。 直近は現状の VPN の代替となる手段の検証と実装、セキュリティアラートの監視最適化、 DLP を活用した情報漏えい対策の強化、中長期的にはパスキーを活用した社内パスワードレス化 に向けて取り組んでいく予定です。よい成果が得られた際はまたアウトプットをしていきます。
エンジニア採用中です !
前述の通り、一休の情シスはコンパクトに運営しているため採用をしておらず、現時点で増員の予定もありません。 一方で、ソフトウェアエンジニア、SRE、データサイエンティスト、ディレクターなど多くの職種で積極的に採用をしております。
ご興味のある方は以下から Job Description をご覧ください。カジュアル面談もやっています !